| 東京大学大気海洋研究所 海洋無機化学分野 |
大気CO2が少なかった氷期の海 |
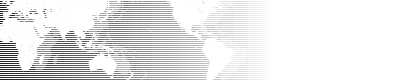
| 1.氷期の大気中二酸化炭素濃度減少の謎 |
地球環境の詳細な変動記録は氷河の氷の中にひっそりと残されていた。ボーリングで氷床に穴を掘ってゆくと、深くなるにつれてより昔にできた氷が手に入る。その酸素や水素の同位体比の分析から、氷ができたときの地表面の平均気温が推定できることは1960年代からコペンハーゲン大学のダンスガードらの研究で知られていた。氷の中には気泡やダストも含まれており、それらの分析から昔の環境を読み取ることができるかも知れない。まず、空気が閉じ込められているはずであるから、変質をうけないようにうまく取り出せれば大気組成の変動がわかるだろう。しかし、わずかな気泡中の二酸化炭素やメタンなど気体成分についてはまだその測定手法に問題があった。1980年代に入ってようやくその記録を読み出すことにフランスやスイスの研究者が成功し、まず産業革命前は大気中の二酸化炭素濃度は280ppmであったのに対し、最終氷期には200ppm前後で約80ppmも低かったことが南極バード基地の氷床コアーの分析から明らかにされた。引き続いて、南極ボストーク基地の氷床コアーからは、過去42万年にわたる大気中の二酸化炭素やメタンが気温と連動し、いつも氷期にそれらの濃度が低くなる周期的変動をしていることも示された[1]。氷期には陸上植物が減少していたことは明らかなので、その分の炭素と大気から減少した二酸化炭素はいずれも海洋に吸収されていたはずである。このことは深海底堆積物中の有孔虫の炭素同位体比が氷期にδ13C値にして平均0.35‰ほど負の側にずれている(つまり陸上植物の軽い炭素が海洋に加わった)ことによっても支持されている。
だが、どのようにして氷期の海が過剰の二酸化炭素を取り込んだのだろうか。
| 2.溶解ポンプ |
その原因としてまず頭に浮かぶことは、表層水温の低下による二酸化炭素の溶解度の増加である。目には見えないが、大気と海洋表層の間では海面を通して常に気体の交換が行われている。
海水の場合、気体の溶解度は物理化学的平衡によって水温が下がるとわずかながら増し、塩分が濃くなると逆に減少する。氷期には海洋表層の水温が低かったので、大気中の二酸化炭素がより多く海に溶け込み、濃度を減少させたのかも知れない。このメカニズムを「溶解ポンプ」としよう。
その効果は、氷期の海洋環境がどんな状態であったかによって決まる。最終氷期の表面海水の温度は現在より2℃前後低かったことが深海堆積物中の有孔虫化石などの豊富な研究から知られている。一方、大陸氷床が成長したことによって海水準が約120mほど低下した。そのために減少した海水量から、増加した塩分も計算できる。その結果は、両方の効果が相殺して、大気中の二酸化炭素濃度を高々10ppm程度減少させるにすぎないことが判明した。溶解ポンプではとても約80ppmもの減少を説明するのは無理なのである。したがって、海洋中の物質循環における生物的あるいは化学的変化など、他の要因を考えなければならない。
図1は、北太平洋における溶存無機炭素濃度の鉛直分布をそれぞれの支配要因に分けて示したものである[2]。深層水中の濃度は表層水に比べて約20%過剰になっている。これは海洋表層で光を利用して植物プランクトンがつくった有機物や炭酸カルシウムが、死後表層から沈降し深層水中でバクテリアによって分解、または化学的に溶解することによる。つまり、微小な海洋生物は、表層水の溶存無機炭素を体内に取り込み深層へ運んで放出・貯蔵する、いわばポンプの役割を果たしていることになる。氷期には、これら生物の働きによって(たとえば、生物生産量や炭酸カルシウムの生成・溶解過程が変わるなどして)、現在より多量の炭素が主に海洋深層に保持されていたと思われる。そのさまざまな可能性をつぎに考えてみよう。

図1.北太平洋における溶存無機炭素の分布とその濃度を支配する因子.
| 3.生物ポンプ |
海洋の生物生産は光の届く海洋表層(有光層)で行われるが、プランクトンは死後、有機物粒子として深海へ運ばれて表層から除かれるため、その不足した溶存無機炭素の補う形で大気から二酸化炭素が溶け込む。この過程を「生物ポンプ」と呼んでいる。その反応は
.jpg)

図2.氷期と間氷期の海洋循環の違い[2].
| 4.もう一つの微量必須元素:鉄 |
現在、中緯度海域の表層水は植物プランクトンに利用されて栄養塩がほぼ完全に枯渇しているが、リンや窒素が残っていながら生物生産があまり高くならない海域がある。東大平洋の赤道付近や南極周辺などであるが、それらの海域では、最近微量必須元素の一つである鉄が不足しているために生物生産が制限されていることが明らかになってきた。リービッヒの最少律で知られる必須栄養素の中に、カリウムやマグネシウムなどと並んで鉄がある。鉄はクロロフィルの構成元素で植物プランクトンの増殖に不可欠である。しかし、海水中では鉄は主に3価で存在し水酸化物を形成するため、非常に不安定で平均滞留時間が短い。そのため海水中に豊富なカリウムやマグネシウムとは異なり、鉄は測定するのが困難なほど濃度が低い。カリフォルニアのモス・ランディング研究施設のジョン・マーチンがクリーン技術を駆使して分析した結果、表層海水中の鉄の濃度は1ナノモル(10-9モル)以下であり、とくにリン酸や硝酸のようにとくに表層で低いことがわかった。それらの海域で海水を採取し、少量の鉄を加えると活発に植物プランクトンが増殖することから、生物生産の制限要因となっていることが推定された。
もし氷期にそのような海域に鉄が供給されたとすれば、生物ポンプの効率をたかめ大気中の二酸化炭素濃度を減少させたことが期待される。図3に示す氷床コアー中のダストの量が氷期に激増することでもわかるように、氷期には気温が低くく乾燥気候だったため、土壌粒子などが舞い上がりやすい状態だった。そのダス卜に含まれた鉄が大気を通して現在の富栄養低クロロフィル海域に運ばれ、海水に溶出して生物生産を高めたことが容易に想像されるのである。
しかしながら、これら生物ポンプのメカニズムの詳細はともかく、生物生産の変化に伴う有機物の深層へのフラックスの増加で大気中の80ppmの減少を説明しようとする試みにはどうしても越えられない大きなハードルがあった。それは、深層水中での有機物の酸化分解には溶存酸素が使われるが、あまりに有機物粒子の沈降が多くなると深層水の酸素が消費しつくされて酸欠状態になってしまうということである。これは、深海の相当部分がヘドロ状態になることを意味し、氷期にも原生動物である底棲有孔虫が生きていたことを示す深海堆積物の記録と明らかに矛盾する。

図3.グリーンランドのキャンプセンチュリー(左)とダイ3(右)の氷床コアの酸素同位体比およびダスト含量の変動記録.
| 5.アルカリポンプの働き |
そこで残る可能性は、炭酸カルシウムの生成と溶解のバランスが変わることによって大気中の二酸化炭素が海に吸収されたのではないかとする考えである。サンゴが二酸化炭素の吸収源という人には頭を冷やして考えていただくこととして、その二酸化炭素吸収の原理は中和反応で示され、溶存酸素は関係せず、アルカリ度が増加をする。したがってアルカリポンプと呼ぶが、この過程は、深海が過剰の炭素を貯蔵しても無酸素状態にならずにすむ今のところ唯一の解決策なのである。
海洋表層の海水は炭酸カルシウムに対して過飽和の状態にあり、有孔虫、円石藻、サンゴなどの生物が炭酸カルシウムを生成する。つまり、上記の反応が右から左へ進む。一方、深海では圧力がかかり炭酸カルシウムの溶解度が増すことや有機物の分解のために二酸化炭素の分圧が高くなることから、ある深度を越えると未飽和になり、沈降してきたプランクトンの炭酸カルシウム殼は溶解する。表層海水のアルカリ度が氷期に高かったことは、二酸化炭素の大気と海水間の物理的な溶解平衡から計算で求めることができる。図4に示すように最終氷期の表層海水は、産業革命前に比べてpHは0.15程度、またアルカリ度は110マイクロ当量程高かったことがわかる。そこで氷期にはなんらかの理由で、炭酸カルシウムがよく解けるようになったのではないかとする説が出された。たとえばマサチュセッツ工科大学のE.
A.ボイルによれば、生物生産が高くなって海底に到達する有機粒子のフラックスが増大し、その分解によって
生じた二酸化炭素が海底の 炭酸カルシウム を溶解を加速することが考えられる。その結果、深層水のアルカリ度が増加し、その海水が海洋循環によって表層に出て大気に接すると
二酸化炭素を吸収することになる。具体的にその効果を論じた論文もその後いくつか発表されている。しかし、たとえこのように深海底で
炭酸カルシウム の溶解が増えたとしても、その影響が大気に現れるには海洋循環の時間スケールから考えて少なくとも数百年はかかるに違いない。しかし、氷床コアの
二酸化炭素濃度や泥炭コアの炭素同位体が示す大気 中の二酸化炭素濃度 の変動は
わずか20〜30 年で起っているのである。つまり、この深海底炭酸塩溶解説だけで説明するのには無理があるといえよう。

図4.大気と平衡にある表層海水のアルカリ度(a)とpH(b).
| 6.シリコン仮説 |
そうこうする中で野崎は新しい解決策を思いつき、大場と共同で論文に発表した[3]。つまり、深海での炭酸カルシウムの溶解が増えたのではなく、その殼をもつプランクトンの増殖が抑制されたのではないかと考えたのである。表層海水にリンや窒素など他の栄養塩があれば、溶存ケイ素がある場合にはオパール(無定形ケイ酸塩)の殼をもつ珪藻が優先的に繁殖することは以前から知られていた。ケイ素が欠乏してなお他の栄養塩が残っている場合に円石藻が増殖する。栄養塩の奪い合いでは、炭酸カルシウムの殻を持つ円石藻はなぜかケイ藻に引けを取るという自然界の摂理がある。そのような条件下では、円石藻は必要な窒素やリンを珪藻に奪われて増殖しにくいのではないかと考えたのである。氷期には海洋表層へ運ばれるエアロゾルの量が増大し、そこから溶け出した溶存ケイ素は珪藻の増殖を促進したはずである。
したがって、珪藻が卓越する期間が長くなるとか、あるいは珪藻が栄養塩を使い切ってしまって円石藻が成長できないなどの現象が起これば、(2)
式に照らしてアルカリ度は上昇し、大気 から二酸化炭素 を吸収できることになる。新たな補足を加えてその仮説を述べると次のようになる(図5参照)。

図5.シリコン誘導炭素循環モデルの概略.
(1)カナダ北方の氷河崩壊(ハインリッヒ・イベントに対応)で北大西洋表層に淡水が流入し、熱塩循環(ブロッカーのコンベヤーベルト)を停止しそうなほど弱めた。その結果、北大西洋での表層水が停滞して沈降しなくなり、メキシコ湾流は北上できなくなってヨーロッパが急速に寒冷化する。
(2)寒冷化によって、乾燥気候となった大地から土壌粒子が舞い上がりやすくなり、海洋表層へのエアロゾルの降下量が増した。つまり、エアロゾルによってもたらされた
ケイ素 が海洋表層に豊富になり、珪藻の増殖を促進すると同時に、炭酸カルシウムの殻をもつ円石藻の増殖を抑制した。
(3)その結果、表層海水における 炭酸カルシウム の生成量が相対的に減少し、沈降粒子の有機炭素/
炭酸カルシウム 比を押し上げる。そして海水のアルカリ度を増加させるとともにpH
が高くなって大気から二酸化炭素を吸収した。
このように海洋表層での過程ならば、20〜30年で大気
中の二酸化炭素濃度 を変化させることも可能だろう。生物の種の交代にはこのように一定のルールがある場合がある。この生物リンケージを通して、化学的には独立した反応である炭酸カルシウム
の生成・溶解サイクルと シリカのサイクルが自然界では巧妙に結びついているようである。
| 7.新たな証拠探し |
最近のモデル計算では、全海洋で生産される炭酸カルシウムが4割減少すれば、シリコン仮説のメカニズムで氷期大気の二酸化炭素濃度の説明が可能といわれる。円石藻と珪藻の種の交代は、リン、窒素、鉄などに対して溶存ケイ素の供給が相対的に不足した海域で実際に起こりうる。北大西洋、赤道大平洋や南極海の南緯45〜50度以北では、溶存ケイ素と硝酸の比が珪藻が必要とする1以下でその候補海域ということになる。最近、コロンビア大学ラモント地球観測研究所のC.D.チャールズらが南極周辺海域の深海堆積物の酸素同位体比とともにオパールと炭酸カルシウム含量を詳しく発表しているが、その一例を図6に示した。堆積物中のオパール含量は、海水を沈降中あるいは海底で埋没するまでの間に溶解されずに残ったほんの一部分にすぎないので、その溶解と保存に関する様々な過程が変われば影響される。しかし、チャールズら[4]は、様々な検討を行った後、オパール含量は主に海洋表層での生物生産を表しているものと結論している。同様の仮定は、炭酸カルシウムについても成り立つであろう。
図6から明らかなように、過去約1万年の間は炭酸カルシウムが卓越しているが、1万9千年から2万5千年の最終氷期の時代には炭酸カルシウムは数%にまで後退し、珪藻が主になることがわかる。珪藻と円石藻の種の交代が起っていることは、図7に示すオパールと炭酸塩のきれいな逆相関関係からも推定できる。また、過去1万年の間は約90%が生物性炭酸塩とオパールで占められているが、最終氷期には20〜25%でその他は陸から運ばれた粘土鉱物などである。堆積物の年代から陸起源微小粒子の堆積速度を計算すると、氷期の方が現在の間氷期より1桁大きい。氷期に露出した陸棚からはこばれたものも含まれるかもしれないが、大部分は大気を経由して運ばれたものと思われる。

図6.南大洋深海コアの炭酸カルシウムとオパール含量の変動[5]
図中の数値は千年の単位の年代を表す.

図7.V22−108コアの炭酸カルシウムとオパール含量の関係.
参考文献:
[1] Petit J. R. et al. (1999), Climate and atmospheric
history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica.
Nature 399, 429-436.
[2] 野崎義行 (1994)、地球温暖化と海、東京大学出版会、p196.
[3] Nozaki, Y. and T. Oba (1995) Dissolution of
calcareous tests in the ocean and atmospheric carbon dioxide, In: Biogeochemical
Processes and Ocean Flux in the Western Pacific. H. Sakai and Y. Nozaki,
eds., TerraPub., Tokyo, p83-92.
[4] Charles C.D. et al.(1991) Biogenic opal in Southern
Ocean sediments wver the last 450,000 years: Implication to surface water
chemistry and circulation, Paleoceanography 6, 697-728.